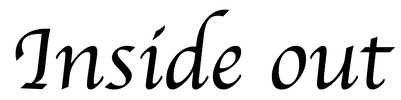インナーブランディングとは、企業の理念を明確にして企業内に浸透させることで社員の士気を高め生産性を上げるきっかけになるものだ。
その好例が、映画伊丹十三作品『スーパーの女』によく描かれている。
ネタバレになるけど、みていきたい。
目次
インナーブランディング前の「スーパー」
舞台となるスーパー「正直屋」は、青息吐息の状態である。
なぜなら、近所に激安スーパーが出店して客を全てかっさらっているからだ。
激安にはカラクリがあって、食品偽装による価格操作が行われていた。
儲けることしか頭にない経営に対して、スーパーを消費者としてこよなく愛好する主人公の女性が立ち上がる。
彼女は正直屋を消費者のためのスーパーに生まれ変わらせるのだ。
正直屋も、古い食品を使いまわしていたり、偽装や業者との裏取引が横行している上、経営者は2代目ボンボンで覇気がなく、職人の言いなり。
従業員たちも自分の仕事に誇りが持てず、長いものには巻かれろとばかりに沈黙を保つ。
けれど、従業員一人一人は本心では、そんな不正を良いことだとは思っていないのだ。
社員のモチベーションを上げるもの
店長になった主人公が「日本で一番消費者のことを考えているスーパーを作りたい」と理想を掲げ実際に行動に出る。
単なる売り上げのためだけに、社員を鼓舞するのではなく、なぜそうしたいかを伝え理想を語ることで、社員たちの心も動いていった。
それまで必要悪だと不正も見逃し、嫌々ながら働くことしか知らなかった正直屋の社員たちが、個人のモラルに従い行動し始める。
みな自分の仕事に対して誇りを持ち始めたからだ。
お金のためだけでは働くことの動機としては不十分であるのだ。自分の行為が人を幸せにし、社会に貢献している実感が社員を変えていく。
事なかれ主義がはびこって、部門ごとに分断されて責任を押しつけあっていた現場も、全体のために動き始めることになった。
そして企業は生まれ変わった
社員だけでなく、経営者さえも活き活きと生まれ変わったのは、自らの仕事が社会貢献している実感が得られたからだ。
次から次へと降りかかる問題にも、皆で団結してクリアしていけたのは「消費者に向いた経営をする」というインナーブランディングを掲げたからだ。
全ての人が同じ旗印のもとに立ち上がり、志を一つにしてやりがいともって仕事をし始める。
そんなエネルギーが最終的には、企業買収も遠ざけ、売り上げを向上させていくというエンド。
コミカルに単純化されたストーリーではあるが、ブランディングの有効性と重要性がよく描かれていた。
(出典)